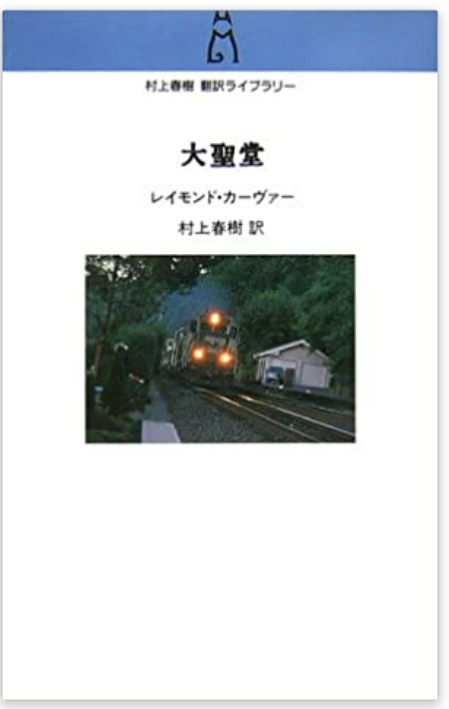【著者について】
1938年オレゴン州生まれ。1983年に「大聖堂」を刊行。1988年肺癌にて死去。
第二次世界大戦の直前に生まれ、物心つくころにはすでに戦争は終わっている世代かな。
【登場人物】
主な登場人物は3人。
・主人公(夫):ほとんど情報が出てこない。
・主人公の妻:ロバートの下で仕事をしたことがあり、文通ならぬテープ通で何年もやり取りしている。元夫との結婚生活時代に空軍基地生活にうんざりして薬の多量内服をしたことがある。
・盲人(ロバート):40代後半で、禿頭で顎鬚をたくわえた男性。盲人のための代読作業の会社?をしていた。
存在について言及はあるが、セリフなどはない人物が2人。
・妻の元夫:空軍の将校。妻の幼馴染。
・ビューラ:ロバートの妻。妻の後釜として働き、その後結婚。8年の結婚生活の後、最近病死した。
あと、バリー・フィッツジェラルドという実在の俳優の名前も登場する。
・主人公(夫):ほとんど情報が出てこない。
・主人公の妻:ロバートの下で仕事をしたことがあり、文通ならぬテープ通で何年もやり取りしている。元夫との結婚生活時代に空軍基地生活にうんざりして薬の多量内服をしたことがある。
・盲人(ロバート):40代後半で、禿頭で顎鬚をたくわえた男性。盲人のための代読作業の会社?をしていた。
存在について言及はあるが、セリフなどはない人物が2人。
・妻の元夫:空軍の将校。妻の幼馴染。
・ビューラ:ロバートの妻。妻の後釜として働き、その後結婚。8年の結婚生活の後、最近病死した。
あと、バリー・フィッツジェラルドという実在の俳優の名前も登場する。
【要約】
主人公夫婦の家に、妻の長年の友人である盲人が訪れることになった。
夫は最初は気乗りしないが、仕方なく付き合っている。
妻は料理の準備やら飲酒やらで疲れて寝てしまい、夫と盲人の二人で何となくテレビを視聴している。
すると、テレビで大聖堂が映し出されて解説がなされる。
盲人は、大聖堂というのはどんなものかを教えてくれと夫に言う。
夫は口であれこれ説明するが、うまく伝えられない。
そこで盲人は、描いてみることを提案する。
ペンを持った夫の手に盲人が手を重ね、その状態で大聖堂の絵を描く。
妻が途中で目を覚まし、二人の様子を見て「いったいぜんたい何しているの?」「どうなってるの?」と言う。二人は構わず続ける。
途中から夫は目を閉じる。すると盲人の指やざらざらとした紙の触覚が伝わってくる。
最後に夫は言う。「たしかにこれはすごいや」。
*最後のセリフについて
夫は最初は気乗りしないが、仕方なく付き合っている。
妻は料理の準備やら飲酒やらで疲れて寝てしまい、夫と盲人の二人で何となくテレビを視聴している。
すると、テレビで大聖堂が映し出されて解説がなされる。
盲人は、大聖堂というのはどんなものかを教えてくれと夫に言う。
夫は口であれこれ説明するが、うまく伝えられない。
そこで盲人は、描いてみることを提案する。
ペンを持った夫の手に盲人が手を重ね、その状態で大聖堂の絵を描く。
妻が途中で目を覚まし、二人の様子を見て「いったいぜんたい何しているの?」「どうなってるの?」と言う。二人は構わず続ける。
途中から夫は目を閉じる。すると盲人の指やざらざらとした紙の触覚が伝わってくる。
最後に夫は言う。「たしかにこれはすごいや」。
*最後のセリフについて
最後の文章「"It's really something," I said.」を村上は「『たしかにこれはすごいや』と私は言った」と訳したが、『Carver's Dozen レイモンド・カーヴァー傑作選』(1994年)版のみ、「『まったく、これは』と私は言った」に変えている。この変更についての読者からの問い合わせに対し、村上は次のように述べている。「あとになって読み直すたびに、『これはちょっと違う。やはり訳しすぎたんじゃないか』という思いを抱きつづけていました(僕はけっこう長く物事にこだわる性格なのです)。それで、僕として今では『まったく、これは』というクールな言葉遣いの方が、長い距離をとって眺めてみれば、よりカーヴァーの世界に近いと感じています」
wikiより
【雑感】
目が見えないというのがどういうことなのか、その痛みと、その痛みを越えた心のありようを、夫は我が身のこととして実感することになる。その実感は理性的なレベルで盲人に同情的な妻には理解することのできない、まさにフィジカルな痛みであり実感である。 430p
理性と体験との対比が、夫と妻との対比で語られている。
他者を真に理解するためには、理性で考えるだけではなく、相手の立場を疑似経験してみることが重要だ。
確かに、そのようにも読める。
でも、それだけならわざわざ小説に書く必要はないわけで、それだけじゃない余剰部分があるはず。だいたい、同じ感想を語ったって、二番煎じでつまらない。
どこかのメディアで「この作品を通じて何を伝えたいのですか?」と問われた、どこかの映画監督が語っていた。「そんな一言で言えるなら映画なんて撮らない。わからないから映画で表現しているんだ。」
うろ覚えでセリフは適当だが、こんな感じだった気がする。
というわけで、本書を読んで気になったところをいくつか見てみて、大いに誤読してみることにする。
他者を真に理解するためには、理性で考えるだけではなく、相手の立場を疑似経験してみることが重要だ。
確かに、そのようにも読める。
でも、それだけならわざわざ小説に書く必要はないわけで、それだけじゃない余剰部分があるはず。だいたい、同じ感想を語ったって、二番煎じでつまらない。
どこかのメディアで「この作品を通じて何を伝えたいのですか?」と問われた、どこかの映画監督が語っていた。「そんな一言で言えるなら映画なんて撮らない。わからないから映画で表現しているんだ。」
うろ覚えでセリフは適当だが、こんな感じだった気がする。
というわけで、本書を読んで気になったところをいくつか見てみて、大いに誤読してみることにする。
①登場人物の名前について
登場人物の中で名前が出てくるのは、盲人夫婦だけ。
(バリー・フィッツジェラルドは、実在するアイルランド人の俳優なので省く。)
主人公夫婦と、妻の元夫については名前が出てこない。
妻と盲人は友人で互いにテープ通をしていたため、お互いの情報を詳しく知っているはずだが、なぜ盲人夫婦の名前しか出てこないのだろうか??盲人夫婦の名前もストーリー上で特に必要なわけではないし、何か意図があるはずだと思う。
やり取りを見返してみると、妻は盲人夫婦について多く語っているが、盲人は主人公夫婦について語る場面は多くない。
そして、妻と盲人がコミュニケーションをとっているときは、妻の方がより多く喋っている気がする。(対して夫と盲人がやり取りしているときには、相対的に盲人のセリフが多い)
つまり、妻・盲人の時は妻優位のコミュニケーションとなっていて、夫・盲人の時は盲人優位のコミュニケーションになっている。
ここから見えてくるのは、妻が盲人を気遣うあまりに自分主導でコミュニケーションしている一方で、夫は相対的に盲人主導でコミュニケーションをとっているという構図である。
障害のある方と接するとき、僕らはどうしてもその人の弱みに目を向けて「何かしてあげる」という目線になりがちで、そうすると自然に「健常者主導」になってしまう。
でも、障害のある方の強みに目を向ければ「当事者主導」でその方から何かを教わることができる。
(バリー・フィッツジェラルドは、実在するアイルランド人の俳優なので省く。)
主人公夫婦と、妻の元夫については名前が出てこない。
妻と盲人は友人で互いにテープ通をしていたため、お互いの情報を詳しく知っているはずだが、なぜ盲人夫婦の名前しか出てこないのだろうか??盲人夫婦の名前もストーリー上で特に必要なわけではないし、何か意図があるはずだと思う。
やり取りを見返してみると、妻は盲人夫婦について多く語っているが、盲人は主人公夫婦について語る場面は多くない。
そして、妻と盲人がコミュニケーションをとっているときは、妻の方がより多く喋っている気がする。(対して夫と盲人がやり取りしているときには、相対的に盲人のセリフが多い)
つまり、妻・盲人の時は妻優位のコミュニケーションとなっていて、夫・盲人の時は盲人優位のコミュニケーションになっている。
ここから見えてくるのは、妻が盲人を気遣うあまりに自分主導でコミュニケーションしている一方で、夫は相対的に盲人主導でコミュニケーションをとっているという構図である。
障害のある方と接するとき、僕らはどうしてもその人の弱みに目を向けて「何かしてあげる」という目線になりがちで、そうすると自然に「健常者主導」になってしまう。
でも、障害のある方の強みに目を向ければ「当事者主導」でその方から何かを教わることができる。
子どもの教育でも同じことが言えると思う。
もちろんこれはどちらが良くてどちらが悪いという話ではないけど、そんな視点から見ることもできるかなと思った。
②食事について
食事のシーンがかなり印象的。
我々はまさにかぶりついた。テーブルの上にある食べ物と名のつくものは残らずたいらげた。まるで明日という日がないといった感じの食べ方だった。我々は口もきかずに、とにかくたべた。我々はがつがつと貪り食い、テーブルをなめつくした。まことに熾烈な食事だった。 390p
直前の飲酒や喫煙のシーンは普通だったのに、なぜかこのシーンだけ異常な熱量である。
これに関して考察したものはネット上ではこれしか見当たらなかった。
https://onl.bz/5ggRmd9
このサイトでは、食事シーンは味覚の象徴であり、
「五感が健在な私と、五感のうちの視覚という重要な要素を封じられた盲人とが、味覚・嗅覚・聴覚・触覚を駆使しながらコミュニケーションを図っていく心の交流の物語」
なのだと書かれている。
なるほどと思いつつも、味覚だけ過剰に表現されている点はいまいちよくわからない。
あまりこれといった仮説が浮かばない・・・
これに関して考察したものはネット上ではこれしか見当たらなかった。
https://onl.bz/5ggRmd9
このサイトでは、食事シーンは味覚の象徴であり、
「五感が健在な私と、五感のうちの視覚という重要な要素を封じられた盲人とが、味覚・嗅覚・聴覚・触覚を駆使しながらコミュニケーションを図っていく心の交流の物語」
なのだと書かれている。
なるほどと思いつつも、味覚だけ過剰に表現されている点はいまいちよくわからない。
あまりこれといった仮説が浮かばない・・・